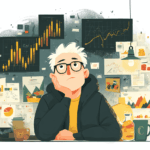はじめに
最近「金(ゴールド)」が話題になっていますよね。
ニュースでも“有事の資産”“インフレ対策”といった言葉をよく聞くようになりました。
ただ、僕自身はまだ金を保有していません。
理由は単純で、「タイミングが難しい」と感じているからです。
それでも金という資産には興味があって、調べるほどに「なるほど、確かに強いな」と思うことも多い。
この記事では、金利上昇下でも金が注目される理由と、
僕のような“保有していない投資家”がどう向き合えばいいのかを整理していきます。
1. なぜ今、金が注目されているのか
金は昔から“有事の資産”と呼ばれています。
戦争・金融危機・通貨不安――そんな時でも価値を保ちやすいのが特徴です。
実際、2020年のコロナショックや2022年のウクライナ情勢でも金価格は上昇しました。
株や債券が下がる中、**「価値がゼロにならない安心感」**が再評価されたんです。
僕が感じるのは、「人間の心理と金の値動きはセット」だということ。
みんなが不安になるほど、金の価値は上がる。
それが“有事の資産”と呼ばれる理由なんだと思います。
2. 金利上昇でも金が下がらない理由
理屈だけで考えると、「金利が上がる=金の価値は下がる」はずです。
なぜなら金は利息を生まないから。
でも現実はもう少し複雑です。
金利が上がる時って、多くの場合「インフレ(物価上昇)」も起きています。
つまり、お金の価値が目減りする局面なんです。
そうなると、
「金利が高くても、お金の価値が下がるなら“現物資産を持とう”」
という動きが出てくる。
結果的に、金利上昇でも金が買われることが起こるんですね。
ここが、初心者には少し分かりにくいけれど、すごく面白いところです。
3. 僕がまだ金を買っていない理由
ここまで調べて「金はやっぱり強いな」と思いつつも、
僕がまだ買っていないのにはいくつか理由があります。
① 利回りがないから
僕は配当重視の投資スタイルなので、「持っているだけでお金が増える」ことを重視しています。
金はそれがない。インカム(収入)ではなく、あくまで“価値保全”の資産です。
② 買い時が難しい
金価格はニュースでもよく取り上げられますが、為替や国際情勢に大きく左右されます。
特に円建ての金は、円安が進むと上がるので、今のような円安局面では「すでに高い」印象もあります。
③ 資産配分とのバランス
僕のポートフォリオは高配当株中心。
電力・銀行・商社といった“生活と連動する業種”が多いので、
金のような守りの資産をどのくらい入れるべきか、まだ自分の中で決めきれていません。
4. それでも気になる「金の存在感」
ただ、保有していなくても、金の動きをチェックしておく価値はあります。
なぜなら、世界経済の“温度計”のような存在だから。
たとえば金価格が急上昇しているときは、
「世界が何かに不安を感じている」可能性がある。
つまり、**リスクオフ(安全資産への逃避)**のサインなんです。
僕も毎週、株価指数と一緒に金価格を確認するようにしています。
持っていなくても、見るだけで“投資家の心理”を感じ取れる。
それが金という資産の面白さですね。
5. 金を持たない投資家が取れる選択肢
「金を買わない」という選択も立派な投資判断です。
ただし、まったく無関心ではなく、“代替手段で備える”ことが大切だと思っています。
🔹 代替策①:インフレに強い高配当株を持つ
たとえば、商社・エネルギー・銀行株。
これらは金利上昇や物価高の恩恵を受けやすい。
僕もこの方向でポートフォリオを組んでいます。
🔹 代替策②:外貨建て資産を少し持つ
金の代わりに、為替分散を意識するのもあり。
米ドル建てETFや外貨MMFなどを通じて、円安リスクを和らげられます。
🔹 代替策③:金ETFを“観察対象”にする
実際に買わなくても、金ETF(1540など)の値動きを見ておくと、
相場全体の“恐怖指数”が見えてきます。
6. 僕の考える「金×配当」の理想バランス
もし将来的に金を買うなら、
僕は「資産の5〜10%程度」を目安にすると思います。
ただし、目的は「増やす」ではなく「守る」。
配当株が資産を育てる“攻め”なら、金は資産を守る“盾”です。
この2つをどう組み合わせるかが、長期投資の安定感を左右します。
今の僕は、まだその“盾”を持っていません。
でも、世界の不確実性を感じるたびに「そろそろ必要かな」と思う瞬間が増えています。
7. まとめ|「持っていない」からこそ見える景色
金を保有していなくても、投資家として学べることはたくさんあります。
僕の場合、
- 金は“資産の温度計”
- 保有はしていないけれど、観察は欠かさない
- 高配当株で“増やす”、金で“守る”発想は常に意識している
という感じです。
「金を持っていない=無関心」ではなく、
金を理解しておく=備えの一歩だと思っています。
これからの不安定な時代、僕も少しずつ“守りの投資”を取り入れていきたいです。
※この記事は僕自身の投資スタイルをもとにした内容です。投資判断は自己責任でお願いします。